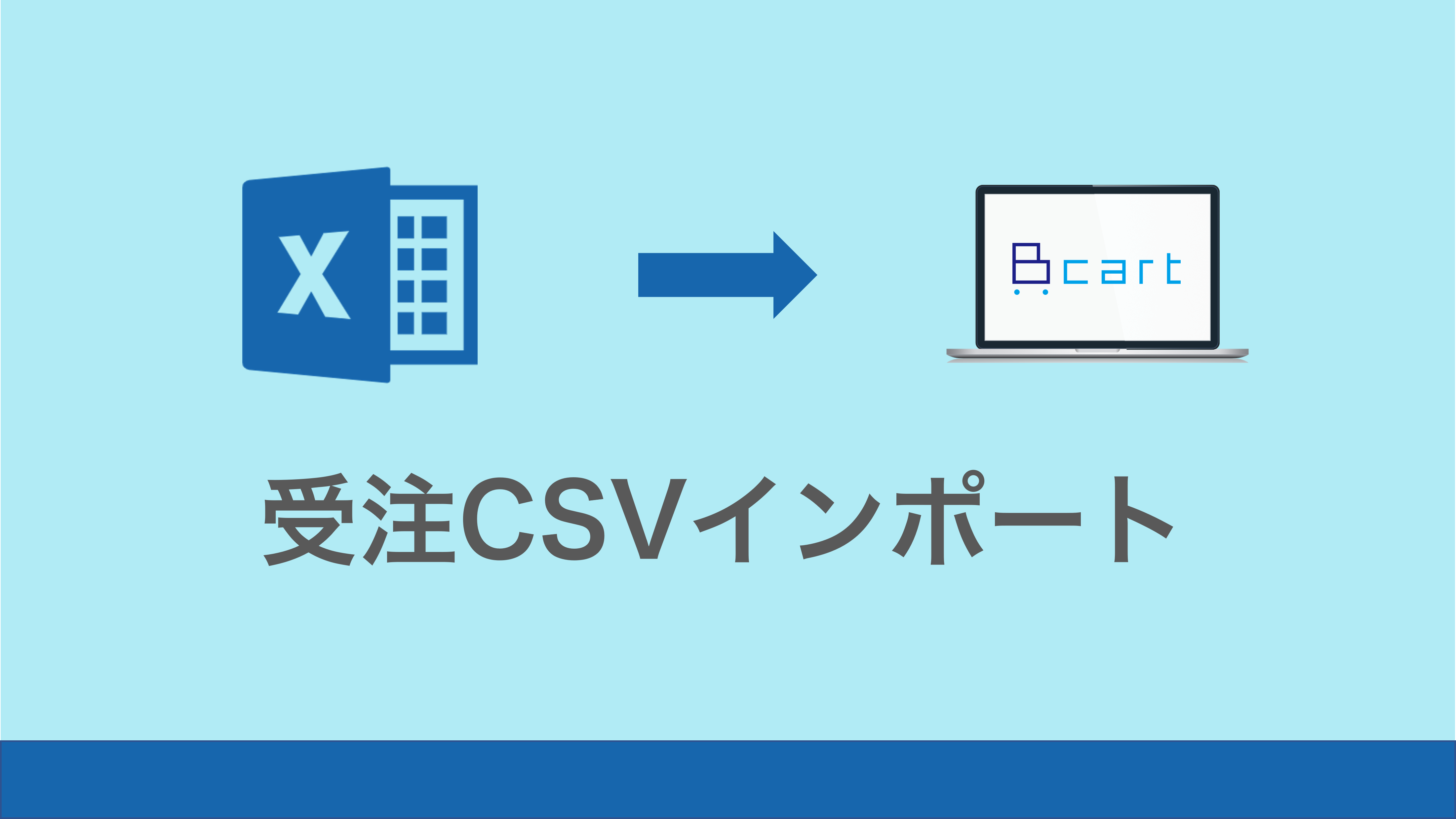【2025年最新】BtoB EC市場は514兆円超!成長する理由とは?@経済産業省データ参照

受注業務の自動化は、人的ミスの削減や業務効率化に繋がります。この記事では、RPAや受発注システムといった自動化の具体的な方法と、それぞれのメリット・デメリットを分かりやすく説明します。 自社に最適なツールの選び方や導入成功のポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
取引先からの注文を受け、内容を確認し、社内システムに入力する。こうした一連の受注業務は、企業の売上に直結する重要なプロセスですが、多くの手作業が発生するため、課題を抱えている企業も少なくありません。人的ミスによるクレーム、特定の担当者への業務集中、非効率な作業による残業の増加など、心当たりはないでしょうか。
これらの課題を解決する有効な手段が「受注業務の自動化」です。
本記事では、受注業務を自動化するメリットから具体的な方法、そして導入を成功させるためのポイントまで、分かりやすく解説します。
受注業務に潜む課題とは?
多くの企業で、受注業務は日々のルーティンとして行われていますが、その裏には見過ごされがちな課題が潜んでいます。自動化を検討する前に、まずは自社の業務にどのような課題があるのかを正確に把握することが重要です。
人的ミスによる手戻りやクレームの発生
電話での聞き間違い、FAXの読み間違い、システムへの入力ミスなど、手作業が介在する限り、人的ミスを完全になくすことは困難です。
しかし、ひとつのミスが誤った商品の発送や納期の遅延に繋がり、顧客からのクレームや信頼を失う可能性があります。また、ミスの修正や再発防止策の検討には多大な時間と労力がかかり、結果として生産性を大きく低下させる原因となります。
特定の担当者に依存する業務の属人化
「この取引先の注文は、Aさんでないと分からない」「特殊な注文の処理方法を知っているのはBさんだけ」といった状況は、業務の属人化を招きます。特定の担当者が休んだり退職した場合、業務が滞ってしまうリスクを常に抱えることになるのです。
また、業務が標準化されていないと、新人の教育に時間がかかったり、担当者間で品質にばらつきが出たりする問題も生じやすくなります。
アナログな作業による業務の非効率化
FAXで届いた注文書を一枚一枚確認し、手作業で販売管理システムに入力する。このようなアナログな業務フローは、多くの時間を必要とします。
とくに、月末や繁忙期に注文が集中すると、担当者は受注処理に追われ、残業が常態化することも少なくありません。本来であれば、より付加価値の高い業務に時間を割くべきですが、非効率な作業がその機会を奪ってしまっているのです。
受注業務を自動化するメリット

受注業務の課題を解決する鍵となるのが「自動化」です。
システムを導入し、業務を自動化することで、企業は多くのメリットを享受できます。
| メリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| 人的ミスの削減 | システムが正確に処理するため、入力ミスや転記ミスがなくなり、商品の誤発送や請求ミスを防ぎます。 |
| 業務効率化 | 24時間365日稼働するシステムにより、処理速度が向上し、担当者の作業時間を大幅に削減します。 |
| コア業務への集中 | 単純作業から解放された従業員は、顧客対応の質の向上や売上拡大施策など、より創造的な業務に注力できます。 |
| 顧客満足度の向上 | 注文から納品までのリードタイムが短縮され、迅速かつ正確な対応が可能になることで、顧客からの信頼が高まります。 |
人的ミスの削減による品質向上
システムは、あらかじめ設定されたルールに従って正確に業務を遂行します。そのため、人間が介在することで発生しがちな入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを劇的に削減可能です。
これにより、誤った商品の発送や請求ミスといったトラブルが減少し、業務品質が安定します。結果として、クレーム対応などの付帯業務も減り、ポジティブな業務サイクルが生まれます。
業務効率化による生産性の向上
これまで担当者が手作業で行っていたデータ入力や転記作業をシステムが代行することで、業務時間は大幅に短縮されます。システムは24時間365日稼働するため、営業時間外や休日に受けた注文も自動で処理することが可能です。
これにより、担当者は受注の締め作業に追われることなく、余裕を持った業務遂行が可能になり、企業全体の生産性向上に貢献します。
コア業務へのリソース集中
受注データの入力といった定型的な作業から解放されることで、担当者はより付加価値の高い「コア業務」に時間とエネルギーを集中させることができます。
たとえば、顧客からの問い合わせに丁寧に対応したり、過去の購買データを分析して新たな提案を行ったりするなど、売上向上に繋がる活動に注力することが可能です。これは、従業員のモチベーション向上にも繋がります。
迅速な対応による顧客満足度の向上
業務が自動化されることで、注文受付から在庫確認、納期回答、出荷指示までの一連の流れがスムーズになります。これにより、顧客へのレスポンスが早くなり、納品までのリードタイムも短縮されます。
迅速かつ正確な対応は、顧客に安心感を与え、満足度の向上に直結します。満足度の高い顧客はリピーターとなり、長期的に安定した取引関係を築くことができるでしょう。
受注業務を自動化する具体的な方法
受注業務を自動化するには、いくつかの方法があります。
それぞれに特徴があり、予算や解決したい課題に応じて最適な手段を選択することが重要です。
Excelマクロ(VBA)による自動化
多くの企業で利用されているExcelの「マクロ(VBA)」機能を使えば、受注業務の一部を自動化できます。
たとえば、特定のフォーマットの注文データを一覧表に自動で転記したり、簡単な集計を行ったりできます。企業で使用されているパソコンには、デフォルトでExcelがインストールされているケースが多いため、低コストで始められるのがメリットです。
ただし、複雑な処理には限界があり、作成やメンテナンスには専門知識が必要です。また、Excel内での自動化に留まるため、特定の担当者に依存しやすく、業務の属人化を助長するリスクもあります。
RPAによる定型業務の自動化
RPA(Robotic Process Automation)は、人間がPCで行う定型的な操作をソフトウェアロボットに記憶させ、自動で実行させる技術です。メールで受信した注文データをシステムに転記する、特定のWebサイトから情報をダウンロードするなど、複数のアプリケーションをまたぐ作業を自動化できます。
既存のシステムを変更することなく導入できる点がメリットですが、業務フローに変更があった際のメンテナンスや、エラー発生時の対応が必要です。
AI-OCRによる紙媒体のデータ化
FAXや手書きの注文書を扱っている場合に有効なのがAI-OCRです。
AI-OCRは、スキャナで読み取った画像から文字情報を認識し、テキストデータに変換する技術です。AI(人工知能)の活用により、従来のOCRよりも高い精度で、手書き文字や非定型のフォーマットも読み取ることが可能になりました。これにより、紙媒体の注文書を扱う際のデータ入力作業を大幅に削減できます。
ただし、読み取り精度は100%ではないため、最終的な目視確認が必要になる場合があります。また、手入力の手間は減るものの、それ以降の処理・管理については結局人の手で行う必要があり、自動化という意味では物足りない・・・と感じるケースも多いでしょう。
受発注システムによる業務全体の効率化
受注から在庫管理、出荷、請求まで、一連の業務プロセス全体をデジタル化し、効率化するのが「受発注システム」です。取引先はWeb上の専用画面から直接発注でき、そのデータはリアルタイムでシステムに反映されます。
これにより、データ入力の手間が不要になるだけでなく、取引先も好きなタイミングで発注できるようになります。業務全体の可視化やデータの一元管理が可能となり、受注業務における多くの課題を根本的から解決できる方法といえます。
【関連記事】受発注システムとは?簡単わかりやすく解説|Bカート
【あわせて読みたい!】無料資料ダウンロード
BtoB ECとは?ITが苦手でもわかる!受注デジタル化入門書
web受発注の実現に最適な「BtoB EC」を超カンタン解説。
「BtoB EC導入診断チェックシート」&「BtoB EC用語集20選」の付録も!
受注業務の自動化におけるデメリットと注意点

受注業務の自動化は多くのメリットをもたらしますが、導入を成功させるためには、事前にデメリットや注意点を理解しておくことが不可欠です。
| 注意点 | 具体的な内容 |
|---|---|
| コスト | システムの導入には初期費用や月額利用料がかかります。費用対効果を慎重に見極める必要があります。 |
| 業務プロセスの見直し | 既存の非効率な業務フローをそのままシステム化しても効果は限定的です。導入を機に業務の標準化が必要です。 |
| 取引先への協力依頼 | 発注方法の変更など、取引先への協力が必要な場合があります。丁寧な説明と移行サポートが重要です。 |
システム導入・運用にかかるコスト
自動化ツールやシステムの導入には、初期費用や月額のライセンス料といったコストが発生します。
高機能なシステムほど高額になる傾向があるため、自社の課題解決に必要な機能を見極め、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
自動化によって削減できる人件費や、ミスの削減による損失額などを試算し、投資に見合うリターンが得られるかを判断しましょう。
業務プロセスの見直しと標準化の必要性
現在の業務プロセスが非効率であったり、担当者ごとにやり方が異なったりする場合、そのままシステム化しても十分な効果は得られません。
システム導入を成功させるには、まず既存の業務フローを可視化し、無駄な工程をなくしたり、ルールを統一したりする「業務の標準化」が不可欠です。これは、システム導入を機に業務全体を最適化する良い機会とも言えます。
取引先への理解と協力依頼
とくに受発注システムを導入する場合、取引先にも新しい発注方法に切り替えてもらう必要があります。一方的に変更を強いると取引先が戸惑い、最悪の場合、取引が停止してしまうリスクも考えられます。
なぜシステムを導入するのか、それによって取引先にどのようなメリットがあるのか(24時間発注可能になる、発注履歴が確認できるなど)を丁寧に説明し、理解と協力を得ることが成功の鍵です。
失敗しない自動化ツールの選び方

自社に最適な自動化ツールを選ぶためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
価格や機能だけで判断せず、総合的な視点で比較検討しましょう。
自社の業務フローとの適合性を確認
まず最も重要なのは、導入を検討しているツールが自社の業務フローや商習慣に合っているかを確認することです。
たとえば、特定の業界ならではの複雑な注文方法がある場合、それに対応できるカスタマイズ性があるか。また、将来的に事業が拡大した際にも対応できる拡張性があるかも重要なポイントです。デモや無料トライアルを活用し、実際の使用感を確かめることをお勧めします。
サポート体制の充実度をチェック
システム導入後には、操作方法が分からない、エラーが発生したなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。そのような場合に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかは非常に重要です。
電話やメール、チャットなど、どのようなサポート窓口があるか、対応時間はどうなっているかなどを事前に確認しましょう。導入時の設定支援や、取引先への説明会開催などをサポートしてくれるベンダーもあります。
拡張性と他システムとの連携性を考慮
現在、社内で利用している販売管理システムや会計システムなど、他のシステムとスムーズに連携できるかも重要な選定ポイントです。データがシームレスに連携できれば、二重入力の手間を省き、さらなる業務効率化が実現します。
API連携が可能かどうかなど、システムの拡張性を確認し、将来的な事業全体のデジタル化を見据えた選択をすることが望ましいです。
受注業務の自動化に成功した事例
実際に自動化ツールを導入し、業務改善に成功した企業の事例を見てみましょう。自社の状況と照らし合わせることで、導入後のイメージがより具体的になります。
ここでは、受注を自動化できるシステムかつ、BtoB取引の受注DXに特化したクラウドサービス「Bカート」の導入事例を紹介します。
株式会社Tricco International様
手作業入力から自動化で人的ミスを皆無に
ペット用品の輸入・卸販売を手がける株式会社Tricco International様では、FAX・電話・メール・LINEなど多岐にわたる受注ルートが業務を圧迫していました。日々の受注管理業務が複雑で、取引量が増えるほど現場の負荷が増す状況にありました。
同社はBカートを導入し、手作業で行っていた商品情報の入力を自動化することに成功しました。導入後は人的ミスが大幅に減少し、売上が倍増しても現場スタッフの負荷は増えず、大幅な生産性向上を実現しています。さらに「送料無料あといくら表示」やおすすめ商品表示機能により、まとめ買いやついで買いが増加し、客単価が30%向上という成果を達成しています。
ロジザード株式会社様
小口リピート取引の効率化でヒューマンエラーを解消
WMS(倉庫管理システム)のクラウドサービスを提供するロジザード株式会社では、ユーザー向けのサプライ品受注業務が属人化している課題を抱えていました。FAXやメールでの受注では文字が不鮮明なケースが多くあり、担当者の経験則に依存した対応が必要でした。
同社はBカートを導入し、小口かつリピート取引の効率化を図りました。導入後はFAX受注を行っていたユーザーのほとんどがBtoB ECサイト経由での受注に移行し、商品情報・受注数量・販売単価などを正確にデータとして把握できるようになりました。注文書の文字が読めない、請求金額を間違うなどのヒューマンエラーをなくすことに成功し、売り手・買い手双方にとってwin-winな受発注フローを構築しています。
【関連記事】ロジザード株式会社様の導入事例|Bカート
まとめ

受注業務の自動化は、単なる効率化ツールを導入するだけではありません。
人的ミスや属人化といった長年の課題から企業を解放し、従業員が付加価値の高い仕事に集中できる環境を整えるための重要な経営戦略です。
自社の課題を明確にし、適切なツールを選び、丁寧な導入プロセスを踏むことで、生産性や顧客満足度の向上という大きな果実を得ることができるでしょう。この記事が、あなたの会社の受注業務改革の第一歩となることを願っています。
電話やFAXによるアナログな受注業務から解放されませんか?
Bカートは、BtoBの受発注業務を自動化できるEC構築システムです。手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、24時間365日、自動で注文を受け付ける体制を構築できます。月額9,800円から利用でき、バックオフィス業務の劇的な効率化を実現。コア業務に集中できる環境作りをサポートします。