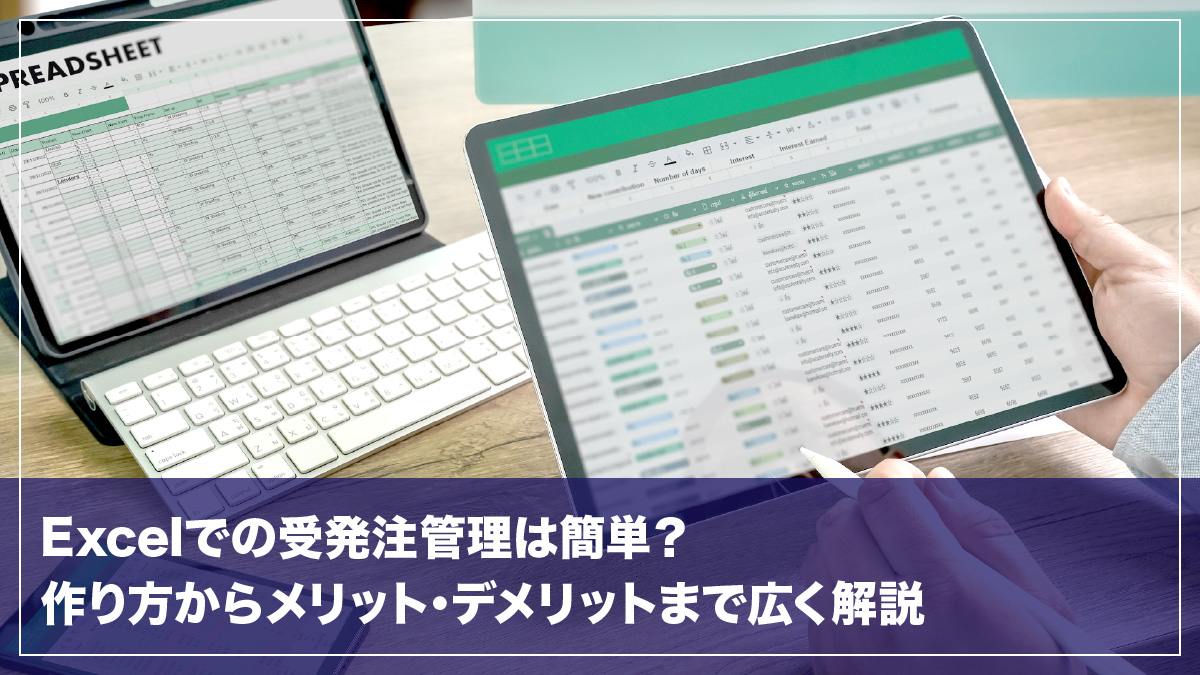【2025年最新】BtoB EC市場は514兆円超!成長する理由とは?@経済産業省データ参照
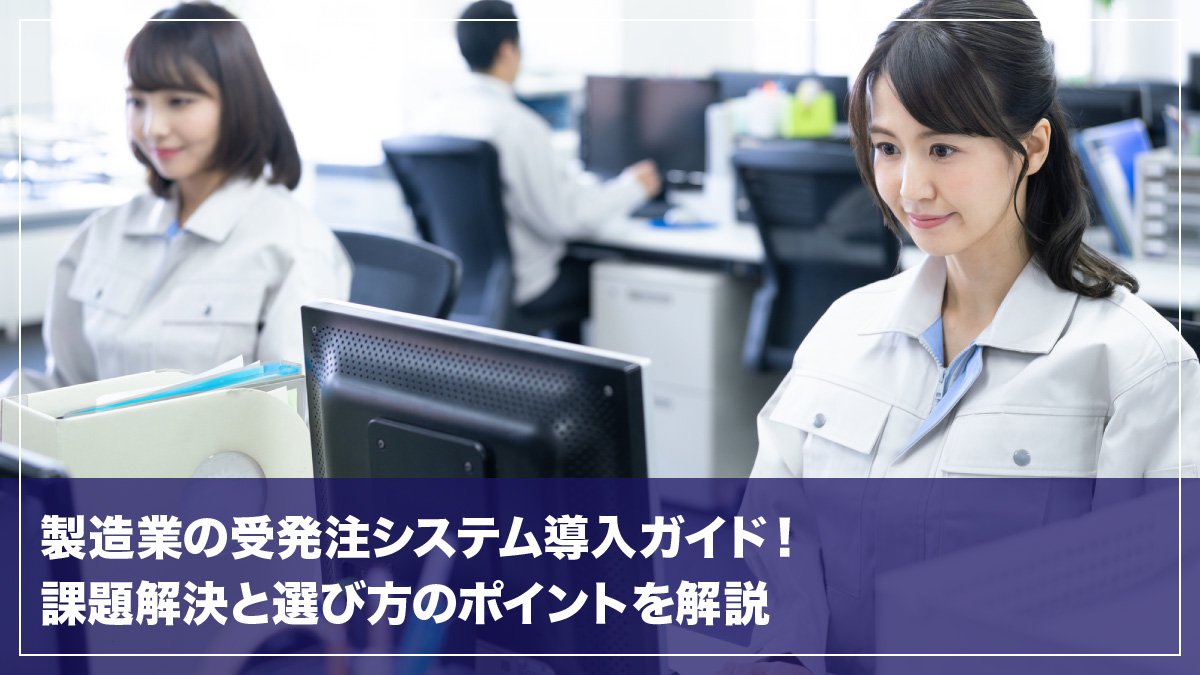
DXやデジタル化が叫ばれて久しい現在ですが、製造業においては、電話やFAX、メールを使ったアナログな受発注業務が、依然として多いのが現状です。しかし、アナログな対応は手間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーや情報、業務の属人化といった多くの課題を抱えています。本記事では、こうした製造業特有の課題を解決する「受発注システム」について、そのメリット・デメリットから、自社に最適なシステムの選び方までをわかりやすく解説します。業務効率化とDX推進の第一歩として、ぜひ参考にしてください。
製造業が抱える受発注業務の根深い課題とは?
多くの製造業では、各会社ごとに長年にわたり確立された業務フローが存在しますが、その中にはデジタル化の波に乗れず、非効率なままとなっているケースも多いでしょう。とくに受発注業務においては、アナログな手法だと、さまざまな課題が生じます。これらの課題を正しく認識することが、解決への第一歩となります。

【課題01】属人化しやすいアナログな管理体制
特定の担当者だけが、取引先とのやり取りや複雑な注文内容を把握している状況は、製造業の現場で頻繁に見受けられます。「いつもの商品を〇〇個ください」といった、担当者にしかわからない注文が入るといったこともあります。
この状態だと、担当者が不在の場合に業務が滞ってしまったり、担当者が退職した際にノウハウが失われたりするリスクがあります。このような属人化は、アナログな管理体制が引き起こす典型的な課題と言えます。
【課題02】多発するヒューマンエラーと確認工数の増大
電話での聞き間違いや、FAXの文字が不鮮明で読み間違えるといったヒューマンエラーは、アナログな業務において避けがたい問題です。注文内容に誤りがあれば、手戻りが発生し、生産計画にも影響を及ぼしかねません。また、ミスを防ぐための二重、三重の確認作業は、従業員の負担を増やし、本来集中すべきコア業務の時間を圧迫する原因となります。
【課題03】電話やFAXによるコミュニケーションの限界
「言った・言わない」のトラブルや、大量の注文を処理する際のFAX送受信の手間は、多くの担当者を悩ませている問題です。受発注対応の多くが電話やFAXで行われると、関係各所への情報伝達が遅れたり、漏れたりする可能性があります。これにより、誤った仕様での納品や納期遅延に繋がるリスクが高まるのです。
【課題04】複雑な在庫管理と曖昧な納期調整
アナログな管理だと、受注情報がリアルタイムで在庫情報に反映されないこともあるため、欠品や過剰在庫が発生しやすくなります。正確な在庫状況を把握できないまま受注してしまうと、結果的に顧客に提示した納期を守れなくなる事態に陥ります。こうした曖昧な納期管理は、顧客からの信頼を損なう大きな要因となります。
【関連記事】受発注事務はきつい?7つの理由と明日から楽になる具体的な対処法を解説!|Bカート
製造業が受発注システムを導入する5つのメリット
受発注システムの導入は、前述した課題を解決し、企業の生産性を大きく向上させる可能性を秘めています。ここでは、システム導入によって得られる具体的なメリットを5つの観点から解説します。

【メリット01】受発注業務の効率化と処理スピードの向上
システムを導入することで、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業が自動化されます。担当者は単純作業から解放されるため、より付加価値の高い業務に集中することが可能です。注文データはシステム上で一元管理されるため、処理スピードが格段に向上し、リードタイムの短縮にも繋がります。
【メリット02】人為的ミスの削減による対応コストの圧縮
システムを介してデジタルデータでやり取りを行うため、電話での聞き間違いやFAXの誤読といったヒューマンエラーを根本からなくすことができます。ミスが減ることで、手戻りや再生産にかかるコスト、そして顧客への謝罪や調整といった無駄な対応コストを大幅に削減することが可能です。
【メリット03】リアルタイムな情報共有で納期遵守率を改善
受注情報、在庫状況、生産進捗といった情報がシステム上でリアルタイムに共有されるため、全部門が常に最新の状況を把握可能です。これにより、正確な在庫引当や納期回答が可能となり、納期遵守率の向上が期待できます。顧客からの問い合わせにも、迅速かつ正確に回答できるようになり、顧客満足度の向上にも貢献します。
【メリット04】業務の属人化解消とノウハウの標準化
受発注に関するすべてのやり取りやデータがシステム上に記録として残るため、業務プロセスが標準化されます。これにより、特定の担当者に依存することなく、誰でも一定の品質で業務を遂行できる体制が整います。担当者の急な欠勤や異動、退職があっても、スムーズに業務を引き継ぐことが可能です。
【メリット05】24時間受注対応による販売機会損失の防止
BtoB ECなどのWeb上で機能する受発注システムであれば、企業の営業時間外や休日でも注文を受け付けることが可能になります。 これにより、顧客の都合の良いタイミングで発注してもらえるようになり、これまで取りこぼしていた可能性のある販売機会を確実に捉えることができます。
【関連記事】受発注システムとは?業務効率化できる主な機能やメリット・デメリットをわかりやすく解説 | Bカート
【あわせて読みたい!】無料資料ダウンロード
BtoB ECとは?ITが苦手でもわかる!受注デジタル化入門書
web受発注の実現に最適な「BtoB EC」を超カンタン解説。
「BtoB EC導入診断チェックシート」&「BtoB EC用語集20選」の付録も!
製造業が受発注システム導入前に知るべきデメリットと対策
受発注システムの導入は多くのメリットをもたらしますが、事前に理解しておくべきデメリットも存在します。ここでは、代表的なデメリットとその対策について解説します。
【デメリット01】システム導入と運用にかかるコスト
システムの導入には、初期費用や月額利用料などのコストが発生します。オンプレミス型の場合はサーバー構築費用も必要です。これらのコストを負担に感じる企業も少なくないでしょう。
【デメリット02】既存の業務フロー変更と従業員への教育
新しいシステムの導入は、これまでの業務フローの変更を伴うことがほとんどです。従業員は新しい操作方法を覚える必要があり、一時的に負担が増加する可能性があります。変化に対する抵抗感から、導入がスムーズに進まないケースもあるでしょう。
【デメリット03】取引先への協力依頼と調整の必要性
自社だけがシステムを導入しても、取引先が従来通り電話やFAXでの発注を続ける場合、効果は半減してしまいます。すべての取引先にシステム利用を強制することは難しく、協力を得るための調整が必要になります。
受発注システム導入前に知るべきデメリットと対策
受発注システムには様々な機能が搭載されていますが、ここでは製造業においてとくに重要となる基本的な機能を紹介します。自社の課題解決に必要な機能が備わっているか、システム選定時の参考にしてください。
| 機能分類 | 主な機能 | 概要説明 |
|---|---|---|
| 受注関連 | 受注管理機能 | Webからの注文を自動で取り込み、受注データを一元管理します。 |
| 在庫関連 | 在庫管理機能 | 受注情報と連携し、リアルタイムで在庫数を更新・管理します。適正在庫の維持に役立ちます。 |
| 顧客情報 | 顧客・取引先管理機能 | 取引先情報や過去の取引履歴、単価設定などを管理します。 |
| 帳票関連 | 見積書・請求書作成機能 | 受注データをもとに、各種帳票を自動で作成・発行します。 |
受注管理機能
WebサイトやEC、EDIを通じて受けた注文情報を自動でシステムに取り込み、一元的に管理する機能です。受注日、顧客名、品番、数量、希望納期などのデータが自動で登録されるため、手入力の手間とミスを削減します。
在庫管理機能
受注が入ると自動的に在庫を引き当て、リアルタイムで在庫数を更新します。現在の在庫数だけでなく、入出荷予定も考慮した有効在庫数を可視化することで、欠品による機会損失や過剰在庫のリスクを低減します。
顧客・取引先管理機能
取引先の基本情報(社名、住所、連絡先など)や、過去の取引履歴、取引先ごとの特別単価などを管理する機能です。これにより、問い合わせへの迅速な対応や、スムーズな取引が可能になります。
見積書・請求書作成機能
受注データや顧客情報をもとに、見積書や納品書、請求書といった各種帳票を自動で作成する機能です。BtoB ECサイトであれば、カートに入っている商品をもとに、発注者(買い手)自身が見積書を発行することもできます。帳票作成にかかる時間を大幅に短縮し、請求漏れなどのミスを防ぎます。
失敗しない!製造業向け受発注システムの選び方
数ある受発注システムの中から、自社に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、とくに製造業がシステム選定で失敗しないための4つの確認事項を解説します。

自社の業態や特有の商習慣に対応可能か確認する
製造業といっても、既製品を生産し販売する見込み生産のほか、受注生産、個別設計生産など、その業態はさまざまです。また、業界特有の商習慣(たとえば、単価の事後決定や支給品の管理など)も存在します。システムの機能が、自社の業態や商習慣に柔軟に対応できるかどうかを必ず確認しましょう。カスタマイズの可否やその範囲も重要な選定基準となります。カスタマイズしなくても運用方法でカバーできるケースもあります。
現在使用している基幹システムと連携できるか確認する
すでに会計システムや生産管理システムといった基幹システムを導入している場合、受発注システムとスムーズに連携できるかは非常に重要です。データの二重入力は非効率の極みです。API連携やCSV連携など、どのような方法でデータ連携が可能なのかを事前に確認し、シームレスな情報共有が実現できるシステムを選びましょう。
導入後のサポート体制は充実しているか確認する
システムの導入はゴールではなくスタートです。運用中に発生した疑問やトラブルに迅速に対応してくれる、手厚いサポート体制が整っているかを確認しましょう。電話やメールでの問い合わせ対応はもちろん、定期的なフォローアップや活用セミナーの開催など、ベンダーが提供するサポートメニューを比較検討することが大切です。また、近年はAIの発展により、AIを活用したサポートを実用化しているベンダーも存在します。最新の技術を積極的に取り入れているかどうかも判断材料になるでしょう。
堅牢なセキュリティ対策が講じられているか確認する
受発注システムでは、自社だけでなく取引先の重要な情報も扱います。そのため、情報漏洩やサイバー攻撃からデータを守るための堅牢なセキュリティ対策は必須条件です。通信の暗号化(SSL/TLS)、IPアドレス制限、多要素認証といったセキュリティ機能が備わっているか、必ず確認してください。
【あわせて読みたい!】無料資料ダウンロード
BtoB ECとは?ITが苦手でもわかる!受注デジタル化入門書
web受発注の実現に最適な「BtoB EC」を超カンタン解説。
「BtoB EC導入診断チェックシート」&「BtoB EC用語集20選」の付録も!
【事例紹介】受発注システムで業務改善に成功した製造業
受発注システムを検討するうえで、実際に受発注システムを導入した他社の事例を確認することも大切です。
今回は、BtoBに特化したECサイトを立ち上げ、受発注業務を効率化できる「Bカート」を導入し、業務改善だけではなく、売上向上まで実現した製造企業の事例を紹介します。
タイヘイ化成株式会社様:効率化はもちろん、新規販路の開拓も
ビニール製品の製造・加工やアクリル樹脂を使用したグッズのOEM生産を手がけるタイヘイ化成株式会社様は、従来の展示会中心の営業活動の費用対効果が低下していることが課題でした。同社は2018年4月にBtoB ECサイト「Bカート」を導入し、展示会で行っていたOEM受注をWeb経由に移行。顧客ごと・商品ごとに細かく価格設定できる機能を活用し、約250品目の商品ラインナップを展開しています。導入後は約150社の新規法人との取引が開始され、対面営業時にもBカートサイトを活用した提案が可能になりました。長年取引のある既存顧客には従来のFAXや電話での受注を継続。BtoB ECサイトと並行運用することで、多様な顧客ニーズに柔軟に対応できる体制を構築しています。
まとめ

製造業における受発注システムは、単なる業務効率化ツールではありません。アナログな業務プロセスから脱却し、DXを推進することで、企業の生産性や競争力を高めるための重要な経営基盤です。本記事で紹介したメリットや選び方を参考に、自社の課題解決に繋がる最適なシステム導入を検討してください。
製造業の複雑な受注業務にお悩みであれば、Bカートを検討しませんか?BtoB取引に特化したクラウド受発注システム(BtoB EC)です。取引先ごとの価格設定や、Web上での見積書発行といった商習慣にも柔軟に対応でき、APIで既存の基幹システムとの連携も可能です。単なる受発注システムではなく「法人向けECサイト」を立ち上げられるため、新規顧客開拓や客単価アップ施策としても活用できます。月額9,800円から、属人化しがちなアナログ業務を効率化しませんか。
■ 【コラム】受発注業務のペーパーレス化は必須!導入のメリットと具体的な進め方を解説
■ 【コラム】受注業務の自動化を実現する方法とは?メリットと注意点を徹底解説
■ 【コラム】【2026年版】BtoB ECとは?基礎知識からDXや売上向上事例を交えて解説
■ Bカート無料トライアルのご紹介 (リクエストはコチラから)
■ Bカートの資料でBtoB ECのはじめ方を知る (無料ダウンロードはコチラから)