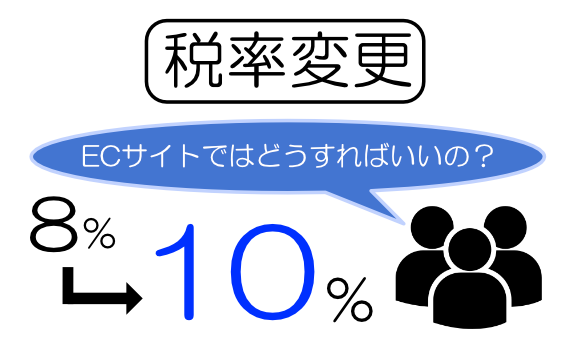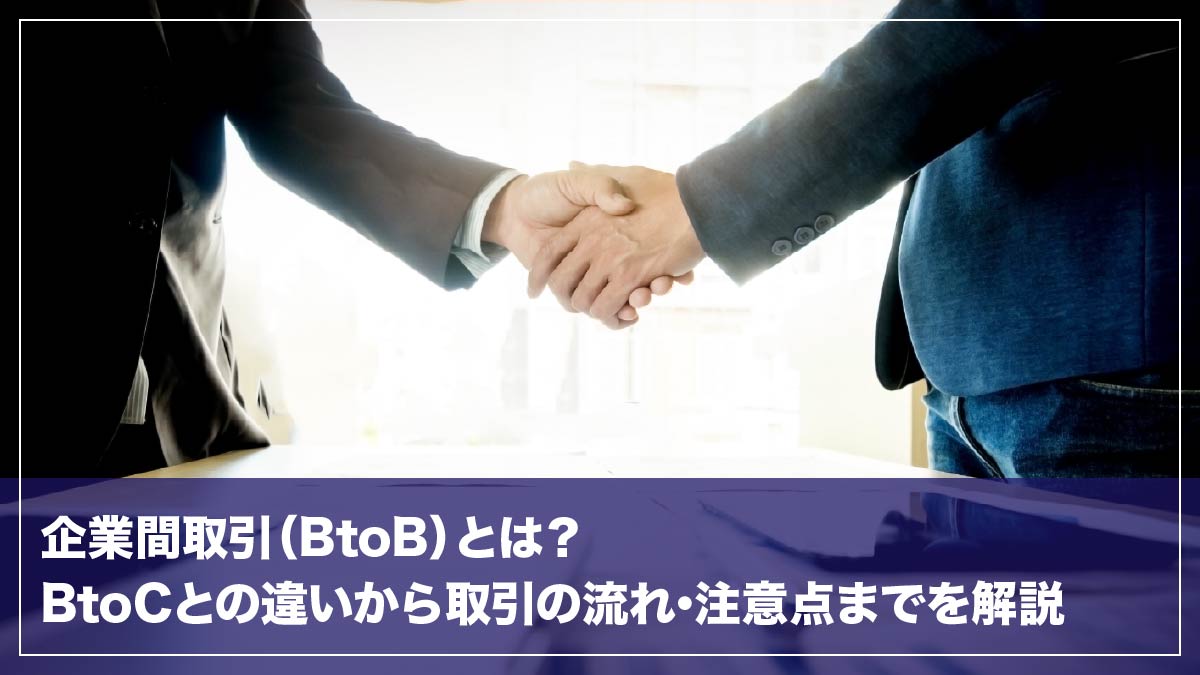【2025年最新】BtoB EC市場は514兆円超!成長する理由とは?@経済産業省データ参照
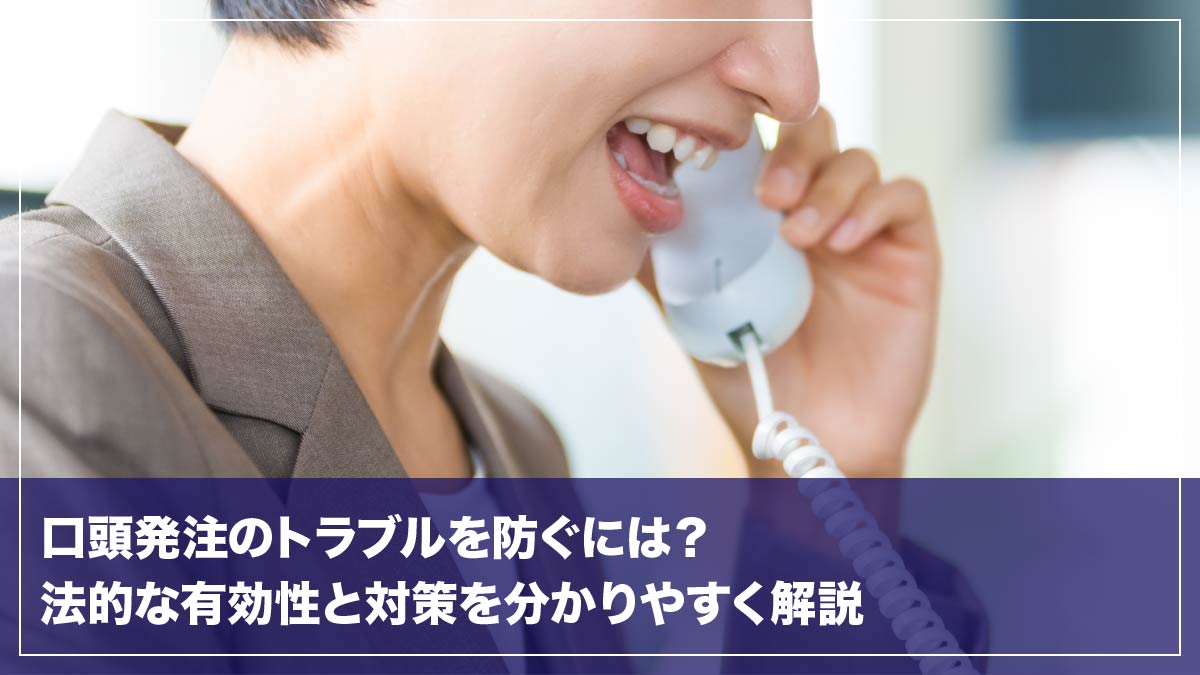
口頭発注による「言った言わない」のトラブルにお困りではありませんか。この記事では、口頭発注の法的な有効性から、実際に起こりがちなトラブル事例、そして万が一発生した際の具体的な対処法までを詳しく説明します。トラブルを未然に防ぐための実践的な予防策も紹介していますので、安心して取引を進めるためにぜひ参考にしてください。
急ぎの案件や長年の付き合いがある取引先とのやりとりで、つい電話や対面での「口頭発注」が行われるのはよくあることです。口頭でのやり取りは、手軽でスピーディーであるものの、「言った・言わない」のトラブルを引き起こす大きな原因となります。最悪の場合、取引先との信頼関係を損ない、事業に深刻な影響を及ぼす可能性も否定できません。
この記事では、口頭発注に潜むリスクと法的な有効性に加え、具体的なトラブル事例や万が一の際の対処法、さらに将来のトラブルを未然に防ぐための予防策まで、分かりやすく解説します。
口頭発注とは?

口頭発注は、発注書などの書面を交わさずに、対面での会話や電話など、口頭でのやり取りのみで注文を行う方法です。手軽さから日常的に行われることもありますが、その法的な意味合いを正しく理解しておくことが重要です。
口頭でも契約は成立する(諾成契約とは)
「書面がないから契約は成立していない」と考える方もいるかもしれませんが、法律上はそうではありません。日本の民法では、当事者双方の意思表示が合致すれば、原則として書面がなくても契約が成立すると定められています(民法第522条)。
つまり、発注者(申込者)が「これをお願いします」と伝え、受注者(承諾者)が「分かりました」と応じた時点で、法的には契約が成立しているのです。
| 契約成立の要件 | 説明 |
|---|---|
| 申込みの意志表示 | 発注者が特定の内容(商品、数量、金額など)で契約を申し入れること |
| 承諾の意志表示 | 受注者がその申込みの内容を了承し、契約を締結する意思を示すこと |
| 意思の合致 | 申込みと承諾の内容が一致していること |
なぜ口頭発注はトラブルに発展しやすいのか
法的に有効であるにもかかわらず、口頭発注がトラブルの原因になりやすいのは、やり取りの「証拠」が残らないためです。人間は忘れたり、聞き間違えたり、あるいは自分に都合よく解釈してしまったりすることがあります。書面という客観的な記録がないため、後になって双方の認識にズレが生じた際に、どちらの主張が正しいのかを証明することが極めて困難となってしまうです。
これが「言った・言わない」の水掛け論や、より深刻な紛争へと発展する大きな要因となります。
【関連記事】受発注事務はきつい?7つの理由と明日から楽になる具体的な対処法を解説! | Bカート ブログ
口頭発注で頻発する4つのトラブル例

口頭発注は、具体的にどのようなトラブルを引き起こすのでしょうか。
ここでは、現場で頻繁に発生する代表的な4つの例を紹介します。自社の状況と照らし合わせながら、リスクを再認識しましょう。
「言った言わない」で水掛け論になる
最も典型的で多いのが、この「言った・言わない」のトラブルです。
たとえば、納品後になって「この商品は頼んでいない」「この金額では聞いていない」といった主張が出てくるケースです。やり取りの証拠がないため、どちらの記憶が正しいかを客観的に証明できず、感情的な対立に発展し、最悪の場合は取引関係の破綻につながります。
注文内容の認識が食い違う
仕様が複雑な製品やサービスの場合、口頭での説明だけでは細部まで正確に伝わらないことがあります。その結果、納品したものが発注者のイメージと全く異なる、といった事態が発生してしまうのです。
たとえば、「いい感じに仕上げて」といった曖昧な内容での注文・受注は、双方の解釈に大きな隔たりを生む原因となり、作り直し・再発送にかかる費用や時間で深刻な揉め事に発展する恐れがあります。
納期や金額で深刻な対立が起きる
「できるだけ早く」といった曖昧な納期設定や、金額の内訳(税抜か税込か、送料はどちらが負担するかなど)を明確にしないまま受注すると、後で大きなトラブルになります。受注者側は自社の都合の良いように解釈し、発注者側は期待していた納期や金額と異なる結果に不満を抱くことになり、支払い拒否などの深刻な対立を引き起こす可能性があります。
追加費用をめぐり関係が悪化する
プロジェクトの進行中に仕様変更や追加作業が発生することは珍しくありません。その際、追加費用に関する合意を口頭のみで済ませてしまうと、発注者側は後で請求書を見て驚くことになる可能性があります。「その作業にそんなに費用がかかるとは聞いていない」「サービスでやってくれると思った」といった主張がなされ、信頼関係にひびが入る原因となります。
| トラブルの種類 | 具体的な発生状況 |
|---|---|
| 言った・言わない | 納品後に仕様や金額について「聞いていない」と主張される。 |
| 認識の食い違い | 曖昧な指示により、成果物が発注者の意図と異なるものになる。 |
| 納期・金額の対立 | 納期や支払条件を明確にせず、後から「話が違う」となる。 |
| 追加費用の問題 | 仕様変更時の追加費用について明確な合意がなく、請求段階で揉める。 |
口頭発注でトラブルが発生した際の対処ステップ
もし実際に口頭発注でトラブルが発生してしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
感情的にならず、以下のステップに沿って冷静に対処することが、被害を最小限に食い止め、円満な解決を目指すうえで重要です。
ステップ1:まずは当事者間で冷静に協議する
問題が発覚したら、まずは当事者間で話し合いの場を設けることが第一です。
感情的に相手を責めるのではなく、事実関係を整理し、どこで認識のズレが生じたのかを冷静に確認し合います。この段階でお互いが歩み寄ることができれば、最も穏便かつ迅速な解決が可能です
ステップ2:やり取りの証拠を可能な限り収集する
話し合いで解決しない場合に備え、客観的な証拠を集めることが重要になります。口頭でのやり取りしかなくても、関連する証拠は意外と残っているものです。
たとえば、以下のようなものが証拠になり得ます。
| 証拠の種類 | 具体例 |
|---|---|
| メール・チャット | 注文内容を示唆する過去のやり取り、打ち合わせの日程調整など |
| メモ・議事録 | 打ち合わせ時に取った手書きのメモや、社内共有用の議事録 |
| 見積書・請求書 | トラブルになる前に発行された見積書や、一部支払い済みの請求書 |
| 第三者の証言 | 打ち合わせに同席していた同僚や関係者の証言 |
ステップ3:内容証明郵便で意思を明確に伝える
当事者間での話し合いが平行線をたどる場合、次の手段として内容証明郵便の送付が考えられます。
内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスです。こちらの主張(たとえば、契約内容の確認や支払いの督促など)を正式な形で相手に伝え、しっかりとした対応を促す効果が期待できます。
ステップ4:弁護士などの専門家への相談を検討する
上記の方法でも解決が難しい場合や、被害額が大きく法的な手続きを視野に入れる場合は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。法律の専門家として、状況に応じた最適な解決策を提示してくれるだけでなく、相手との交渉代理や、訴訟になった場合の法的手続きも行ってくれます。早期に相談することで、より有利な条件での解決につながる可能性が高まります。
口頭発注トラブルを未然に防ぐ4つの予防策

一度トラブルを経験すると、その対応に多大な時間と労力、そして精神的なストレスを強いられます。最も重要なのは、そもそもトラブルを発生させないことです。
ここでは、明日から実践できる具体的な予防策を4つ紹介します。
発注書や請書を書面で取り交わす
最も基本的かつ効果的な対策は、発注者側は注文内容を明記した「発注書」を発行し、受注者はそれに対する「請書」を発行することです。 取引の内容が書面として明確に記録され、後の「言った・言わない」を完全に防ぐことができます。また、郵送やFAX・メールで送付をし、双方で保管しておくようにしましょう。
メールやチャットで必ず記録を残す
たとえ電話や対面で話をした後でも、「先ほどお電話でお話しした件ですが、以下の内容でお願いいたします」といった形で、必ずメールやビジネスチャットツールを使ってテキストでも送信し、相手からの確認の返信をもらう習慣をつけましょう。この一手間が、万が一の際の強力な証拠となります。
基本契約書を締結しておく
継続的に取引を行う相手とは、個別の注文に先立ち、取引全般の基本的なルールを定めた「基本契約書」を締結しておくことが有効です。検品の方法、所有権の移転時期、支払い条件、秘密保持義務、トラブル発生時の解決方法などをあらかじめ定めておくことで、個々の取引がスムーズになり、紛争を予防できます。
参考:契約書の参考例 - 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン 厚生労働省
受発注システムを導入し仕組み化する
受注件数が多い場合や、複数の担当者が受注業務を行っている場合には、受発注システムの導入が非常に効果的です。
システム上で受注から納品、請求までを一元管理することで、履歴が自動的に記録され、人的なミスや不正を防ぎます。業務効率化とリスク管理を同時に実現できるため、長期的な視点で見ればコスト以上のメリットがあります。
| 予防策 | メリット | こんな企業にオススメ |
|---|---|---|
| 発注書・請書の交付 | 取引内容が明確になり、証拠として最も確実 | すべての企業 |
| メール等での記録 | 手軽に実施でき、やり取りの証拠を残せる | すべての企業 |
| 基本契約書の締結 | 継続的な取引のリスクを包括的に低減できる | 特定の相手と反復継続して取引する企業 |
| 受発注システムの導入 | 業務効率化と人的ミスの防止を料率できる | 発注件数が多い、または担当者が複数いる企業 |
【関連記事】受発注システムの作り方を解説!エクセルと専用システム導入はどちらが良い? | Bカート ブログ
発注書・注文請書を作成する際に必ず記載すべき必須項目
トラブル防止の要となる発注書や注文請書は、ただ作成すれば良いというものではありません。必要な項目が漏れていると、その効果が半減してしまいます。ここでは、それらの帳票に必ず記載すべき項目を解説します。
注文年月日と管理番号
「いつ」注文された取引なのかを明確にするために、注文年月日は必須です。また、社内で管理するための「注文番号」を振っておくと、後の問い合わせや経理処理の際に特定の取引を素早く見つけ出すことができ、発注側・受注側の両社にとって非常に便利です。
発注者と受注者の基本情報
誰から誰への注文なのかを明確にするため、双方の会社名、住所、電話番号、担当者名を正確に記載します。ここに誤りがあると、帳票そのものの有効性が問われる可能性もあるため、注意が必要です。
注文内容(品名、数量、単価、合計金額)
トラブルの最大の原因となりうるのが、この注文内容です。品名や型番、サービスの仕様、数量、単価、そして消費税を含めた合計金額を、誰が見ても誤解のしようがないように、具体的かつ明確に記載することが最も重要です。
納期、納品場所、支払条件
「いつまでに(納期)」「どこへ(納品場所)」納品するのかを明記します。また、支払いに関しても、「いつまでに(支払期日)」「どのような方法で(支払方法、例:銀行振込)」支払うのかを記載することで、納品や支払いに関するトラブルを防ぐことができます。
記載事項 |
記載する理由 |
|---|---|
注文年月日・管理番号 |
取引の特定と社内管理を容易にするため |
発注者・受注者情報 |
契約当事者を明確にするため |
注文内容詳細 |
品名、数量、金額の認識齟齬を防ぐため |
納期・納品場所・支払い条件 |
契約履行に関する条件を明確にし、トラブルを未然に防ぐため |
【関連記事】受注業務の自動化を実現する方法とは?メリットと注意点を徹底解説 | Bカート
口頭発注のトラブルに関するよくあるご質問(FAQ)
口頭発注に関する具体的な疑問や、いざという時の対応について、とくに多く寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
Q1. 急ぎの仕事で、どうしても電話口で対応するしかありませんでした。
後からできることはありますか?
A. はい、すぐにやるべきことがあります。
電話を切った直後、忘れないうちに「先ほどのお電話の件、念のための確認です」と前置きし、メールやチャットで「注文内容・金額・納期」をテキストで送って記録を残しましょう。相手から「内容に相違ありません」といった簡単な返信をもらえれば、それが強力な証拠となります。
Q2. 発注書を受け取りましたが、請書を発行していません。
契約は成立していないことになるのでしょうか?
A. いいえ、契約は成立しています。
請書がなくても、発注書の内容に従って商品の発送準備を始めたり、サービスの提供を開始したりした場合、その行動によって「承諾した」と見なされ、契約は成立します。ただし、何の反応もなく業務に着手してしまうと、発注側に「契約がきちんと成立しているか」という不安を与えてしまうため、一度確認の連絡を入れるのが安全です。
まとめ

口頭発注は、手軽で迅速な反面、深刻なトラブルを引き起こす大きなリスクをはらんでいます。
法的には有効な契約であっても、証拠が残らないため「言った・言わない」の水掛け論に陥りやすいのが実情です。
本記事で紹介した予防策、とくに「帳票の発行」や「メール等での記録」を徹底するだけで、ほとんどのトラブルは未然に防ぐことができます。円滑で健全な取引関係を継続するためにも、今日から受注プロセスを見直してみてはいかがでしょうか。
口頭発注のトラブルでお困りなら受発注システムとして利用できる「Bカート」が根本的な解決策となります。電話やFAXでの受注による聞き間違い・誤入力といった人為的ミスを削減、正確な受発注を実現できます。また、担当者しか知らない取引条件や価格情報もシステムが一元管理するため、属人化によるトラブルも解消でき業務効率を大幅に向上させることが可能です。
2,000社以上が導入し、口頭発注から脱却して安心できる取引環境を構築できる「Bカート」を、あなたも始めてみませんか。