【2025年最新】BtoB EC市場は514兆円超!成長する理由とは?@経済産業省データ参照
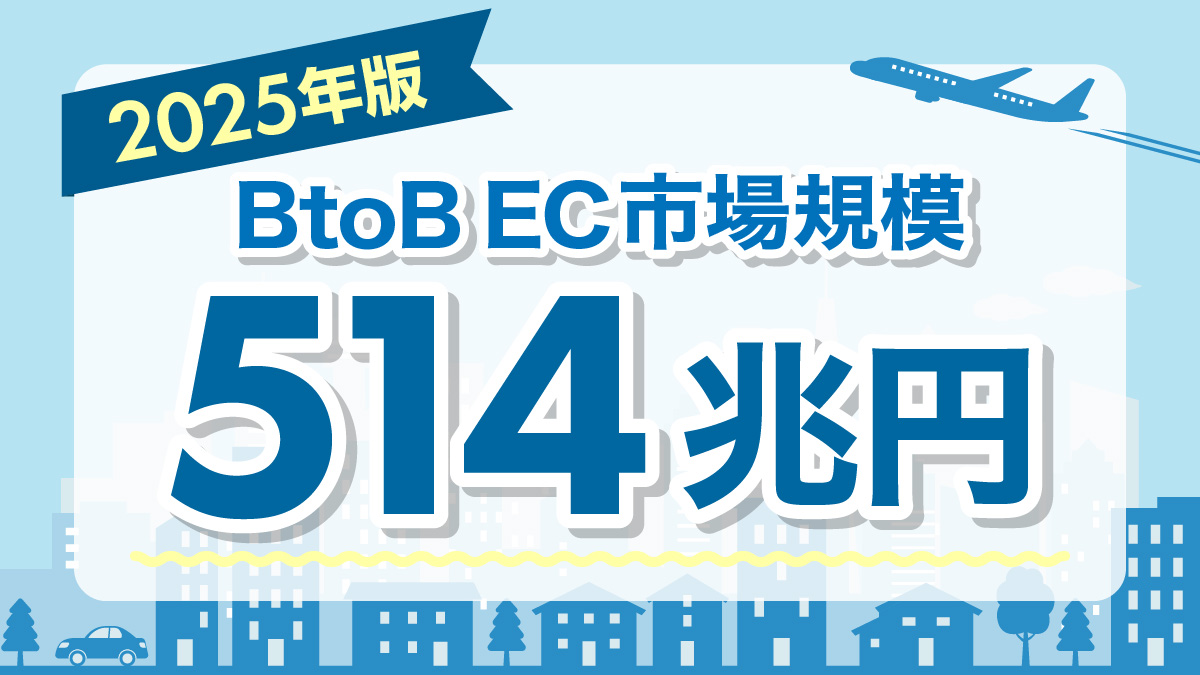
2025年8月、経済産業省は新たに『令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書』を発表しました。この記事では、本報告書をもとに、BtoB ECの市場規模について解説していきます。また、今後の市場動向や注目のトピックなどBtoB ECの「いま」が分かる内容になっていますので、ぜひご一読ください。
1. BtoB ECとは?
近年、BtoB ECが企業の生存や成長のカギを握る、重要な要素となりつつあります。そもそもBtoB ECとは何を指しているのでしょうか?この章で簡単に解説していきます。
BtoB ECとは、企業同士がインターネット上で行う商取引(電子商取引・Electronic Commerce)や、取引を行うためのサービスを指します。似た言葉として、楽天やAmazonに代表される企業と個人の商取引「BtoC EC」、フリマアプリなどを使用して個人間で取引を行う「CtoC EC」が存在します。
ECというと、一般的に「商品を売り買いする仕組み」と捉えられることがありますが、企業同士の商取引であるBtoB ECにおいてはその限りではありません。BtoB ECは、原材料の調達から製造・流通・そして販売に至る「サプライチェーン」の効率化や在庫管理をはじめとした受発注業務の省力化に寄与するシステムなのです。
従来、日本において企業同士の売買や取引は、主にファックスや電話といったアナログな方法が利用されてきました。しかし近年、国際的な競争力の低下や少子高齢化による労働力の減少が取り沙汰されるなか、企業の生産性を向上させるための取り組みとしてBtoB ECの重要性は増しており、企業からの注目も集まりはじめています。
BtoB ECについてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご一読ください!
【関連記事】【2026年版】BtoB ECとは?基礎知識からDXや売上向上事例を交えて解説|Bカート
BtoB ECを説明するうえではずせないのが、EDI(Electronic Data Interchange:電子データ交換)と呼ばれる、企業間で発生する受発注や請求といった定型的な業務を自動化できるシステムです。
一般的な「EC(カートシステム)」は、「商品の売買」を主目的とし、新規顧客の開拓や柔軟な商談にも対応できます。一方、EDIは大量の受発注処理や帳票の自動化・効率化を主目的とし、とくに大企業やサプライチェーンの安定運営に採用されています。現在、EDIの通信に利用されていたISDN回線の終了に伴い、従来のEDIからシステムの乗り換えが進んでいます。経済産業省では、EDIを含めた市場を「BtoB EC市場」として、市場規模を算出しています。
2.BtoB ECの市場規模|前年比49兆円増を記録

出典:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」
2024年、日本国内のBtoB ECの市場規模は514兆4,069億円となり、前年比10.6%増を記録しました。また、商取引全体におけるECの利用率を表す「EC化率」は、3.1ポイント増の43.1%となっています。
BtoB EC市場が成長している理由
2020年以降、 国内のBtoB EC市場規模は成長を続けています。その理由を3つ解説します。
まず1つ目は、新型コロナウイルスの感染拡大により非接触・非対面の需要が増し、業務のデジタル化が進んだことが挙げられるでしょう。企業間取引にも非対面が求められたなか、従来の対面営業を廃止し、社員が自宅からでも対応できるBtoB ECが支持されることとなりました。2025年現在、コロナ禍以降もデジタル化は社会全体で促進されています。
2つ目の理由として、女性の社会進出や働き方改革による「働くことへの意識変化」がBtoB ECの普及を後押ししたと考えられます。たとえば、政府による産前・産後休業の推奨や時間外労働の上限規制などによって、人々のワークライフバランスを求める動きが高まりました。それに加えて労働力不足の影響もあり、企業が人材を安定的に確保するには労働環境を改善する必要が出てきたことで、業務の大幅な効率化を目指せるBtoB ECの需要が増したと考えられます。
最後に、政府による支援政策もBtoB ECの成長要因として見逃せません。日本の国際的競争力の低下に拍車がかかるなか、政府は会社規模でデジタル化を行い業務効率化を実現する「デジタルトランスフォーメーション(DX)」を推し進めています。経済産業省を中心に各種デジタル化推進政策も続々と展開されており、BtoB EC市場成長の追い風となっています。
BtoC ECとBtoB ECの市場比較
企業・個人間での商取引であるBtoC EC市場も拡大を続けています。2024年の市場規模は26兆1,225億円となり、前年から1兆2,790億円の増加となりました。なお、BtoC EC市場はBtoB EC市場と比較すると約19.7分の1程度の規模であり、いかにBtoB ECが巨大市場であるかが分かります。
3. 業界別の市場推移まとめ

出典:経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」
この章では、数ある業界のなかから代表的な5業界を取り上げ、詳しく市場推移をみていきます。
建設:32兆0,585億円
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場規模 | 166,510 | 182,680 | 195,944 | 208,558 | 234,598 | 271,277 | 320,585 | +18.2% |
| EC化率 | 11.0% | 12.0% | 13.1% | 14.3% | 15.2% | 16.9% | 18.3% | +1.4% |
2024年の建設業におけるBtoB EC市場規模は32兆0,585億円で、前年比18.2%となりました。EC化率も18.3%に上昇しています。経済産業省のレポートでは、「広告・物品賃貸」と同じくEC化率が低い結果ですが、市場規模の伸び率は「運輸」に次いで2番目となっています。
食品製造:41兆5,859億円
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場規模 | 244,040 | 266,010 | 264,672 | 271,027 | 296,443 | 355,307 | 415,859 | +17.0% |
| EC化率 | 55.6% | 59.3% | 63.3% | 67.2% | 70.7% | 75.0% | 81.3% | +6.3% |
2024年の食品製造業におけるBtoB EC市場は、前年比17.0%増の41兆5,859億円と大幅な伸長がみられました。これは、インバウンドの増加も背景に外食需要が高まったことが要因と考えられています。また、原料高騰による販売価格の引き上げが市場全体を押し上げたことも理由のひとつです。EC化率も81.3%と、他業種と比較して非常に高い水準となっています。
情報通信:22兆8,688億円
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場規模 | 133,990 | 145,820 | 151,685 | 166,975 | 182,616 | 223,984 | 228,688 | +2.1% |
| EC化率 | 18.8% | 19.9% | 21.0% | 21.8% | 22.3% | 23.4% | 24.2% | +0.8% |
情報通信業のBtoB EC市場規模は22兆8,688億円で、前年比2.1%と微増となりました。EC化率も0.8%増の24.2%と微増。法人企業統計データでは、情報通信業の総売上高は、2023年95兆6,311億円に対し2024年94兆6,392億円に減少しています。売上高が減少するなか、EC化はゆるやかに進んでいるという結果となりました。
運輸:16兆7,543億円
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場規模 | 97,550 | 104,610 | 96,843 | 110,884 | 133,433 | 139,465 | 167,543 | +20.1% |
| EC化率 | 15.9% | 16.8% | 18.2% | 19.2% | 20.9% | 22.5% | 24.9% | +2.4% |
2024年の運輸業BtoB EC市場規模は16兆7,543億円で、前年比は20.1%と大幅な伸びを記録しました。EC化率は24.9%に達しています。
運輸業に関する注目すべきトピックとして、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働時間の上限規制が行われ、トラックの輸送力が不足してしまう懸念が挙げられます(物流の2024年問題)。その対策として、輸配送管理の自動化やデジタル受発注システムの導入が進み、EC市場規模が大きく伸びたと考えることもできます。
卸売:128兆8,684億円
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場規模 | 1,039,510 | 1,026,450 | 920,944 | 1,006,059 | 1,128,794 | 1,212,499 | 1,288,684 | +6.3% |
| EC化率 | 27.7% | 28.8% | 30.6% | 32.3% | 34.9% | 37.5% | 40.3% | +2.8% |
2024年の卸売業におけるBtoB EC市場規模は128兆8,684億円で、前年比6.3%増となりました。EC化率は40.3%に拡大しており、要因として大手流通企業を中心にEDI(電子データ交換)技術の標準化が進んでいるようです。
とくに日本は、商品が消費者に届くまでの間に関わる卸売業者の数が多いことで知られています。そのため、卸売業者のEC化率が増えれば、国全体の物流コストの削減が期待でき、企業の成長や国際競争力向上につながるでしょう。今後も卸売業のEC化率の動向には注目していきたいところです。
4.BtoB ECの市場展望とトピック
経済産業省が発表しているデータをみても、BtoB ECの市場規模が今後も拡大を続けることは明らかです。ここでは、政府が推進する「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」を軸に、BtoB ECの将来展望について考察していきます。
深刻化する人手不足に有効な対策
社会問題となっている「人手不足」。多くの業界で人手不足が常態化しています。とくに、長年の経験と勘に頼りがちな受発注業務は、特定のベテラン社員に依存する「属人化」に陥りやすい領域ともいえます。
BtoB ECは、この課題に対する強力な解決策となります。アナログな業務プロセスをデジタル化・自動化することで、担当者の負担を劇的に軽減し、より付加価値の高い業務にリソースを再配分できます。各社員が付加価値の高い業務に集中できる環境は、「やりがい」も生まれやすく、既存社員の定着率向上はもちろん、採用にも有効となります。BtoB ECの導入は、単なる効率化に留まらず、人手不足の時代を乗り越える経営戦略として選ばれ続けるでしょう。
企業データの「再利用」が加速
近年、DXの推進において重要視されているのが「再利用可能なデータの蓄積」です。急速な変化が求められる現代において、データをどれだけ効率よく再利用できるか、そしてデータをもちいた事業分析ができるかどうかが、企業の競争力に直結しつつあります。さらに、今後は、生成AIなどの技術を組み合わせ、需要予測の精度向上、パーソナライズされた商品推薦、価格の動的最適化といった、より高度な活用が進むでしょう。
BtoB ECをうまく活用すれば、インターネット上に顧客の取引データを貯められるため、他のツールと連携し、高度な経営分析が可能になります。BtoB ECを利用することで、「情報」の数々を、企業戦略を強化する「価値ある武器」に変えることができるのです。AI技術の急速な発展により、この流れは一層強まると予想されるため、BtoB ECの普及も大きく進むとみられます。
カーボンニュートラル促進による影響も
DXを通じたデータの再利用は、世界が目指す「カーボンニュートラル」の実現にも貢献します。カーボンニュートラル実現に向けた国際的な動きが活発になるなか、日本でも「GX(グリーン・トランスフォーメーション)推進法」が成立し、国を挙げた支援が加速しています。
これらの流れから、企業活動に伴うCO2の排出も、いまや世界中で厳しく監視される時代になりました。製造から流通・販売そして廃棄に至るまで、サプライチェーン全体でのCO2排出削減が求められる時代が到来しています。BtoB EC単体ではCO2排出量の削減を直接実現することは難しいですが、BtoB ECの導入を起点に、CO2排出量の見える化と、業務効率化による排出量削減が求められるようになるでしょう。
このように、DX推進とカーボンニュートラルの拡大を背景に、BtoB ECのニーズも増していくと予想できます。むしろ、企業の成長と環境負荷軽減の両立を目指すために、BtoB ECが必要不可欠な要素となっていくのではないでしょうか。ビジネスに関わるすべての人が、BtoB ECの市場規模・市場動向に注目しておくとよいでしょう。
5. BtoB EC導入のメリット・デメリット
BtoB ECの導入は、DXや事業成長を加速させる一方、注意すべき点もあります。ここでは、そのメリットとデメリットを簡潔に解説します。
メリット:業務効率化と売上アップ
BtoB EC導入の最大のメリットは、生産性の向上です。電話やFAXによる受発注業務、手作業でのデータ入力を自動化することで、人的ミスを削減し、担当者はより付加価値の高い業務に集中できる時間を捻出できます。
また、ECサイトは24時間365日稼働するため、営業時間外の受注や、これまでアプローチできなかった新規顧客の獲得が期待でき、新たな販路拡大に直結します。「ついで買い」も起こりやすく客単価の向上も期待できます。蓄積された購買データを分析すれば、顧客1人ひとりに合わせた提案も可能になり、売上アップに貢献します。
デメリット:コストと既存顧客のフォロー
デメリットとしては、まず導入・運用コストが挙げられます。システムの初期費用や月々の利用料が発生するため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。低コストで始められるクラウド型サービスを選ぶのも有効な対策でしょう。
また、長年電話やFAXで取引してきた既存顧客へのフォローも欠かせません。オンラインでの注文に抵抗がある顧客もいるため、導入初期は従来の方法と併用したり、操作方法を丁寧に説明したりするなどの配慮が、スムーズな移行のカギとなります。
6. BtoB ECを軸にしたDXが明暗を分ける
BtoB EC市場は、今後も大きく拡大することが見込まれています。実際、デジタルシフトを積極的に進めることで、業務を効率化し、競争力を高める企業が増えています。
BtoB ECプラットフォーム「Bカート」は、企業がBtoB ECに取り組むうえで必要な機能が揃った、BtoB特化のECサービスです。企業はBカートを導入することで、顧客ごとの受発注データを集積し、分析や連携を行いやすくなり、単なる受発注業務を超えた戦略的なビジネス展開が可能になります。Bカート導入により多くの企業が業務効率化を実現し、ビジネスプロセス全体での改善効果を実感しています。
【BtoB EC導入事例】初の育休取得も!水産業者がBカートでDXを実現
水産業の株式会社豊洲漁商産直市場様は、Bカートを導入し電話・FAX中心の受注業務をデジタル化。注文対応の効率化もあって、客単価1.2倍、売上1.5倍を達成しました。さらに、業務負担の軽減により、社内初の育児休暇取得が実現。DXが企業の成長と、従業員が働きやすい環境の両立を可能にした好事例です。
【BtoB EC導入事例】受発注業務の負担が大幅に軽減、EC化で販路拡大
業務用菓子の卸売を行う株式会社ナゴミヤ様は、Bカート導入でFAX受注から脱却。受注業務を半分の人員で対応可能になりました。さらに、Bカート上で集客活動を行い、新規登録数が倍増。和菓子店だけでなく、飲食店など新たな顧客層の開拓にも成功し、事業拡大の足がかりとなっています。
【関連記事】株式会社ナゴミヤ様の導入事例|BカートこのようにDXへの対応が企業の成長や競争力の強化に直結する重要な要因となっています。本記事を読んでいるあなたも、企業の競争力を高める一助として、BtoB ECの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
■ 【外部リンク】令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書
■ 【コラム】【2026年版】BtoB ECとは?基礎知識からDXや売上向上事例を交えて解説
■ Bカート無料トライアルのご紹介 (リクエストはコチラから)
■ Bカートの資料でBtoB ECのはじめ方を知る (無料ダウンロードはコチラから)





